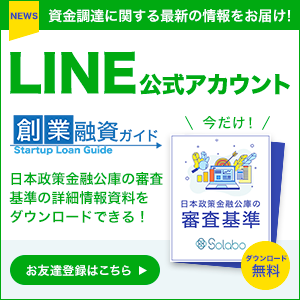個人事業主・法人問わず、事業を行っていると見積書の提出を求められるケースがあるでしょう。
しかし、いざ自分で作成してみると、「見積書ってどのように書けば良いのかな?」と迷ってしまう方が多いようです。
見積書は単に発注内容を相手に伝えるだけでなく、相手に発注する決意を促す役割がありますので、経営者であれば正しい書き方を身につけておくことが大切です。
そこで今回は、見積書の書き方を実際の見本とあわせてご紹介します。
|
個人事業主や中小企業の方は、経営改善のための費用のうち最大20万円までを国から補助してもらえます。 上記の補助を受けるには、早期経営改善計画という中小企業庁の補助制度を利用する必要があります。早期経営改善計画を利用するには税理士や認定支援機関などの専門家を通さなければなりません。 当サイトを運営するSoLaboは、早期経営改善計画の対応可能な認定支援機関です。現状の信用情報で融資を受けられそうかの無料相談も可能なので、融資と経営改善の双方からのご提案が可能です。 |
1.見積書の3つの役割
見積書は、商品や仕事の発注を受けた際、相手方に提出する書類です。
見積書には次の3つの役割があります。
|
①認識の違いを防止する役割:
見積書には価格、支払条件、納品内容を明記することで認識の違いによるトラブルを防止する役割があります。 ②情報伝達の役割: 社内、取引先、そして仕入先など取引の相手と内容・納期の確認を行うという役割があります。 ③発注の決意を促す役割: 見積書があることで正式な金額を認識し、意思決定ができる側面があります。発注の決意を促す役割があります。 |
2.見積書を作るのに必要なもの
見積書を作るのには、以下のものが必要になります。
- 見積書用紙
- 封筒
- 見積書在中のスタンプ
- 切手
見積書用紙や封筒に決まった規格はありませんが、用紙のサイズはA4サイズが一般的です。
封筒や切手は、送付する見積書に合わせたものを用意しましょう。
なお、昨今は書類の電子化が進んでいるため、電子媒体で取引先とやり取りをする際には、これらの準備物は不要です。
3.見積書のフォーマット
見積書に決まったフォーマットはありません。
インターネットで「見積書 テンプレート」と検索すると、無料でダウンロードできる見積書テンプレートが入手できます。また、見積書作成ソフトやツールを利用して見積書を作成することも可能です。
当サイトを運営している株式会社SoLaboでは、無料で利用できる請求書作成ツール「RAKUDA」を提供しております。
会員登録するだけで、見積書をはじめ、請求書や納品書、送付状も作成可能です。
ぜひ一度試しに利用してみてください。
4.見積書の書き方17のポイントと見本
(1)宛先
宛先は相手方の会社名や屋号を記載します。
大きい会社宛の場合は担当者の部署や名前まで書くと良いです。
会社名には「御中」、個人名には「様」と敬称を間違えないように気をつけましょう。
| 【記載例 】
・□□□□□株式会社 御中 ・□□□□□株式会社 代表取締役 □□□□ 様 ・□□□□□株式会社 □□□支店 □□□部 (役職名) □□□□様 |
(2)通番
通番の記載は必須ではありませんが、小売店や建築業など、見積書を出す機会が多い会社の場合、見積書作成ソフトなどのシステムを使うのが一般的です。その場合、データ管理上の目的で「通番」というナンバーをつけられるようになっています。
通番をつけることで、その番号で見積書を検索することができるので管理が楽になります。
また、相手方から受注の連絡や、見積書の再発行の依頼があった場合にも便利です。
(3)発行日または提出日
見積書の発行日または提出日は必ず記載します。いつ行った取引なのかわかるようにするためです。
また、相手方との電話での打ち合わせの時や、受注などの際に、「○月○日のお見積書の件で」と伝えれば通じるようになるためコミュニケーションが円滑になります。
(4)発行者の会社名・住所・氏名
見積書を発行する側の会社名や住所、氏名を記載します。
相手が問い合わせをしやすいように電話番号とメールアドレスも記載しておくと親切です。
(5)発行者の印鑑
印鑑は必須ではありませんが、会社対会社の取引の場合、社印を押すのが一般的です。
(6)タイトル
「御見積書」「見積書」「お見積り」「お見積書」などというタイトルが一般的です。
何の書類かわかるように上部中央に、他の文字よりも若干大きめの文字で記載します。
(7)件名
何の見積書かわかるように記載します。プロジェクト名やサービス名などがある場合には、その名称を記載しましょう。
(8)有効期限
見積書の有効期限を記載することで、価格変動の回避や期限終了後の申込みトラブル防止になります。
【記載例】
|
(9)見積り金額
見積もりの合計金額を税込で記載します。わかりやすく若干大きめに記載するのが一般的です。この金額は明細の合計と合致するように注意しましょう。
(10)品番・品名
商品名やサービスの内容を記載します。
システム開発やデザインなどの場合には、作業を段階にわけて詳細がわかるように明記しましょう。
(11)商品の数量
商品などの場合は、個数を記載します。サービスや提案などの、数量 を書くのが難しい場合は一式と記載します。
(12)商品の単価
商品やサービスひとつあたりの金額を記載します。
(13)商品の金額
数量×単価の金額を記載します。
(14)小計
商品やサービスの税抜の合計金額を記載します。
(15)消費税額
小計にかかる消費税額を記載します。
なお、食料品など軽減税率対象の商品がある場合は、税率ごとに分けて記載が必要です。
(16)合計金額
商品やサービスの税込の合計金額を記載します。見積書の上部に記載した「見積り金額」と一致しているか必ず確認しましょう。
(17)備考
相手方との誤解がないように、上記で説明しきれない納品場所や納期、前提条件などの補足事項を記載しましょう。
①納品場所
商品を納める場所のことです。
例えば「貴社指定場所」、「貴社本店倉庫内」、「貴店舗事務所内」などと記載します。
②納期
「◯年◯月◯日」というように日付を明記する場合と、「正式受注後2週間以内」の様に記載することもあります。
5.見積書でよくあるトラブルと注意点
(1)見積書と内容が違うから支払わない!と言われないように注意する
見積書のトラブルでよくあるのが、「見積書と内容が違うから支払わない」と言って入金をもらえないケースです。納品内容と見積書の記載内容はしっかり合わせるようにしましょう。
(2)安易な納期設定が元でトラブルが起きないようにする
納期のトラブルも当然ですが、非常に多いです。安易な納期を設定しないように、チェック機能を持ちましょう。
(3)見積書の提出が遅すぎて発注を逃さないようにする
トラブルへのリスクを考慮し過ぎて、発注のタイミングを逃さないようスピーディに見積書を提出できる体制を整えましょう。
金額、納期、納品内容で起こりうるトラブルを防止し、スピーディに出すことが重要です。受注出来ることが最重要ですが、しっかりと入金してもらえるように納品内容と納期には充分注意しましょう。
まとめ
発注内容を相手に伝えたり、認識の違いを防止したりする役割がある見積書には記載すべき項目がいくつもあります。
受注に繋がる大切な書類ですので、正しい書き方をしっかりマスターしておきましょう。
請求書・見積書・納品書を簡単便利に作成できる「RAKUDA」
無料で「請求書」「見積書」「納品書」「送付状」「取引管理」が作成できるクラウド請求書ツールです。
請求業務がコレで完結。
面倒な源泉徴収税の計算も自動で行ってくれます。
個人事業主の方には特におススメ!